本は減らない
自宅の書斎はすでに本に埋もれている。天井までの大型の本棚が5台設置されてはいるものの、そんなものはとうの昔に使い果たし、溢れた本は段ボールに詰め込まれて宅内の収納に分散して置かれている。容積、重量、どの点から見ても対策が必要な状況である。
もちろん本自体を減らすという抜本的な対策が必要なのは重々承知であるが、その試みはいずれも挫折してきた。もちろん読み返すことがない本は随時処分しているが、保存する必要がある本は日々増える一方である。
電子書籍への移行は何度か試みてはいるものの、やはり現実的ではない。そもそも、電子化されていない過去の書籍が多すぎる。特に、戦前戦後の古書のコレクションは絶望的である。昭和後期までに対象を広げても、麻雀関係の絶版書籍のなどは電子化しても絶対に採算が取れないので、よほどの数寄者編集者でもいない限り実現しないだろう。電子化された書籍に限っても、数千冊の紙の書籍を買い直すのも現実的ではない。大量に貼られた付箋をどうするかも頭が痛い。さらに言うとサービス終了のリスクが大きすぎる。DRMのない電子書籍であれば多少は購入しているが、Rabooの悲劇を忘れてはいない。
そもそも本というものは本質的に要不要の判断が難しいものである。他のモノであれば1年間使わなかったものはまず不要と割り切って捨てることも可能であるが、本はそうはいかない。何年も開いていない本が突如として必要となって探し回ることも日常茶飯事である。さらにそうなる本を事前に予測することも不可能である。もっと悪いことに、そうした本に限ってあとで入手不可能となるものである。商業的に成功して一度はランキングに顔を出したような本であっても、旬を過ぎて何年も経つと古書としての入手もままならなくなることがよくある。これだけ中古本の流通が進化し、マーケットプレイスで何でも手に入りそうな世の中でも、である。
それでも時折思い立って処分するものの、そうしてできた隙間もあっという間に新刊に食われていく。焼け石に水である。
今までの本棚
今までは14年前に購入したスロフィー4本をメインの本棚として使用してきた。何度も引越を繰り返しながらも、レイアウトを工夫して乗り切ってきた。
長らく使用したこのスロフィーは価格も考えると概ね満足な出来ではあったが、いくつか不満もあった。
- 天井突っ張り部が細めであり、部屋によってはうまく突っ張れないことがあった。RC造の部屋で直接突っ張れるのであればこれでも十分だが、和室を改装した部屋では下地に突っ張れるように置けないこともあった
- 棚板の強度はやはり不足していた。600幅なら厚さ18の繊維板でも大丈夫かとも思ったが、やはり中央部はたわみ、ひどいところではダボから抜け落ちる寸前になっていた。棚板を受けるダボ自体は金属なので大丈夫だったが、棚板側の軸受には傷みが見られた
- 経年のたわみもあり、同じ本棚を4台並べていても間に隙間が生じていた。背板もたわみ、隙間が生じていた
本棚の更新
細かな不満はありながらも、本棚の入れ替えという大事業にはなかなか重い腰が上がらずだましだまし運用を続けてきた。しかしながら、この度の転居先の書斎の天井高が2200と低く今までの本棚が設置できないこともあり、重い腰を上げて一斉更新となった。リビングや子供部屋は天井高が2380のため、スロフィーはそちらで余生を送ることとなる。そこでは本がぎっしりと詰め込まれるのではなく雑貨なども置かれるため、今よりは負荷が減るだろう。
本棚に求めること
さて、新たな本棚の購入だが、ここで改めて自分が本棚に求めるものを整理しておく。
- 倒れない、圧死しない。これが何よりも最重要項目となる。それでも天井までの収納を求めるのであれば、必然的に十分な転倒対策が必要となる
- 本棚は奥行が薄くなければいけない。せいぜい200までが限度で、できれば150程度が望ましい。それ以上深いものは本棚としては使いにくくなる。A4判 (奥行210) やB4判 (奥行257) の大型本を大量に所蔵している場合は例外として、A5判 (奥行148) の単行本以下のサイズが中心の蔵書家ならば絶対に薄い本棚を選ぶべきである。深さ300などの本棚を選ぶと必ず二重に本を置くことになり、奥の本が死蔵される
- 同じデザインで角形2号封筒が入る奥行き300弱程度の書類棚が手配できるとなお良い。書斎には本だけではなく、様々な書類が積まれることとなるため、「超」整理法の角形2号の封筒を大量に収める棚が必要となる。これを本棚と同じデザインで揃えられるとありがたい
- 各段の高さは220が望ましい。これはA5版 (210) が入れば、大半の本が収納できるということを前提にしている。210ギリギリではないのは、多少は遊びがあった方が使いやすいのと、あわよくば菊判 (218-220程度) も収納できたらという思いである
- 材質にもよるが、厚さ20以下の棚板は強度に不安がある。可能であれば25は欲しい
- 棚受けも大事で、棚板をダボに乗せるだけの構造は怖い。棚位置が可変であることよりも強度を重視したほうが良い。実際に組み替えることなどほとんどない
- 幅は600におさめるべきである。800や900の本棚は強度のある棚板を選んでも必ずたわむ。また600を超えると、部屋からの出し入れに苦労する
- 扉などは極力廃するべきである。扉を開ける一手間もその厚みも馬鹿にならない
- 強度の点からも背板はあったほうが良い
- 後から買い足せるものが良い。長年のベストセラーとなっており、今後もしばらくは販売が続きそうなものを選ぶのが良い
選んだ本棚
スロフィーは廃番となっており後継のタナリオも検討したが、融通が効かなそうが点が多く見送った。代わりに選んだのが大洋のShelfitだ。エースラックの名前の方が馴染み深いかもしれない。
- 上置の高さが選べるのがありがたい。1780 + 320の組み合わせで2200に合わせられる。天井突っ張りができるのはもちろん、オプションで突っ張り板が追加できるのも良い (この程度ならば作ったほうが安いが)。
- 厚さ25のタフ棚板が選べるのも嬉しい
- 細かな仕様が公開されているのがありがたい。限られた空間に限界まで本を詰め込みたい人間にはこうしたミリ単位の情報が必須となる
- 高さの選択肢が豊富なのも嬉しい。窓を殺さずに限界まで設置しようとすると、高低さまざまな本棚を組み合わせざるを得ない。また単純な300刻みなどで設定されているわけではなく、標準的な机の高さや腰高窓の高さなどを意識した設定が心憎い。強いてあげるなら881と1170の間にもう一区切りあれば完璧だった
- オプションも豊富に取り揃えられている。幅木よけカット加工、配線裏板穴加工、連結穴加工あたりはありがたい。特に連結穴加工は転倒対策にもなる
- 幅木よけカット加工くらいは標準で対応してくれても良い気もするが
褒めてばかりだったが、実はいくつか難はある。
- 自分で組み立てる家具としては値段はそれなりで、激安というわけではない。質からすると割安ではあると思うが、安さを売りにした自組立家具と高品質な組立済家具に挟まれた微妙な立ち位置ではある
- ラインナップが非常にわかりにくい。Shelfitやエースラックのブランドでの自社販売に加え、OEMで様々な販路を持っているため、どこで買うかが非常に重要になる。値段が変わるだけならばまだしも、販路によっては対応していないオプションがあるのもいやらしい
- 結論から言うと、オーダー収納スタイル楽天店で買うのが多くの人にとって最適解になると思う。Shelfitのブランド名は出ていないが、大洋からの仕入れであることを公言しており、実際に大洋のロゴ入りの段ボールで届く。ほとんどのオプションにも対応してくれる。もちろん楽天のポイントも貯まる
- 棚板移動ピッチが30のため、厚さ25のタフ棚板で組むと、各段の高さは215が基本となる。これが実に微妙なサイズで、四六判やA5判の単行本は入るが、菊判はギリギリで入らない。オプションで棚板移動ピッチを15にすると230を基本にして組めるが、どこかの段にしわ寄せが行き文庫専用になる
- 1780の本棚を25のタフ棚板で組むと、各段の高さは下から201, 215, 215, 215, 215, 215, 219となる。最下段はB6判や四六判が限界で、A5判は入らない。また、菊判以上の判型は最上段や上置に逃がしたりと棚割に工夫が必要となる
- エースラック自体は12色の展開だが、姉妹品のオーダーコンソールはそのうちの限られた色だけしか選べない。セットで揃えたい場合は注意が必要
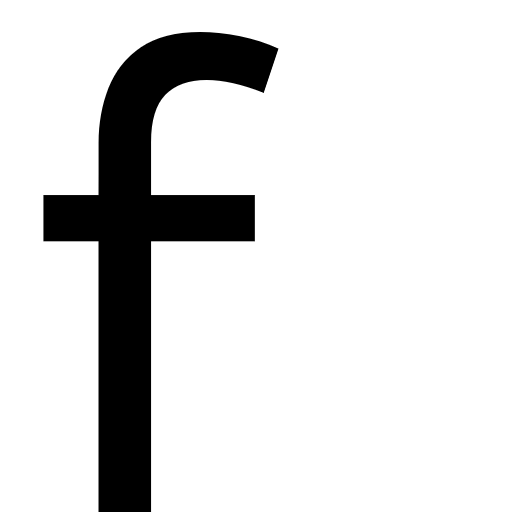
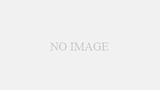
コメント