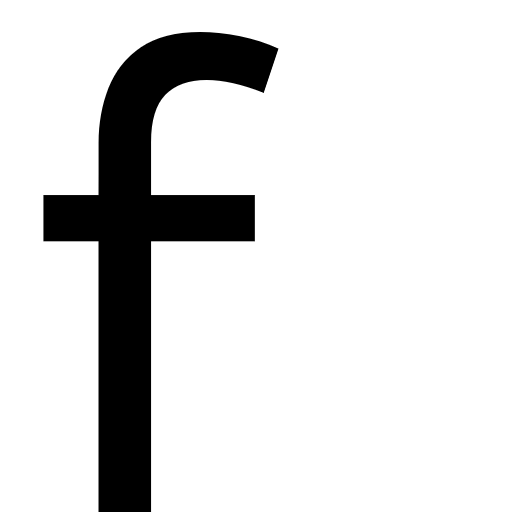小倉博行, ラテン語のしくみ
ラテン語を学びたいというよりはラテン語とはどんなものかを概観したいという気分で読むと、細かな活用型の練習を延々とさせられるのに閉口する。それでも、ラテン語ならではの特徴の話題は楽しめる。
山田敏弘, 日本語のしくみ
他言語と比較をすると、日本語のどの部分が特殊なのかが見えてくる。日本語を特殊な言語とする言説も多いが、多言語とよくよく比べて見ると特殊なところも普通のところもある言語に過ぎない。
- 敬語表現は珍しいものではないが、謙譲語を持っている言語は極めて少ない
- 格助詞を用いることで自由な語順の文を作れるのが特徴。ただし、自然な文にするにはSOV順にすると必要がある
- 多数の一人称が使われる一方で、単数と複数、過去と完了などをあまり意識しない (厳密には人を指す場合やオノマトペには単複の区別が見られる)。すなわち、複雑な区別をする場合と単純な区別しかしない場合がある、普通の言語である
- “~してくれた”、”~でしょう”、”~かもしれない” などのニュアンスを表現する方法が多い
羊齧協会(編), 東京ラムストーリー 羊肉LOVERに捧げる東京&周辺 羊レストランガイド
羊料理専門店を集めたグルメガイド。東京の名の通り首都圏のみだが、かなりマニアックなお店もカバーしている。少々古い本で残念ながら続編は出ていないようだが、羊齧協会は現在も活動中なので、最新情報はこちらで。
ブルース・ブエノ・デ・メスキータ(著), アラスター・スミス(著), 四本健二(訳), 浅野宜之(訳), 独裁者のためのハンドブック
ポリティカルサイエンス本。権力維持の構造は独裁政権だろうと民主主義だろうと同じであるという視点に立つことで新たな発見がある。
政治とは権力を保持することであり、それは独裁政権でも民主主義でも変わりがない。その権力の後ろ盾は名目的な有権者集団 (取り替えのきく者)、実質的な有権者集団 (影響力のある者)、盟友集団 (かけがえのない者) の多層構造になっており、これも政治体制に依らず不変である。独裁政権では言わずもがな小さな盟友集団が実際にリーダーを選んでおり、その他の多くの人々は影響を及ぼさない。民主的な選挙が行われる民主主義国家や多数の株主がいる大企業でも本質は同じであり、大統領選挙人団や大株主の支持なくして権力を保持することはできない。
内容は文句ないが、翻訳は今ひとつ。悪文が多く読みにくい。