税金の成り立ちを追ってみると、租税の仕組みそのものが国家であることがわかる。
著者はまずホッブズとロックの租税論に立ち返る。彼らが租税を国家が市民に提供する便益への対価と定義したことが、国家を形づくったと言える。すなわち、王権神授説から社会契約論にもとづく国家論への転換である。イギリス社会では納税を権利とみなす自発的納税倫理が定着していたのも、この影響が大きい。
一方、無数の領邦国家に分裂していた後進国ドイツでは、イギリスやフランスといった先進国家に対抗して経済的基盤を整えて発展するために租税を必要としていた。これが、納税を義務とする倫理観を形成していく。
上記の二者の対立に加え、後にはさらに経済・社会政策を実施するための政策手段としての租税という第三の考え方が現れる。ニューディール期に先鋭化したこの租税観が民主主義的な手続きによって実現したことは示唆に富む。
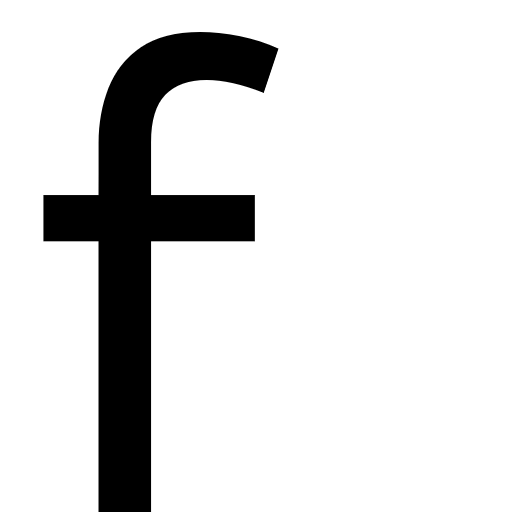

コメント