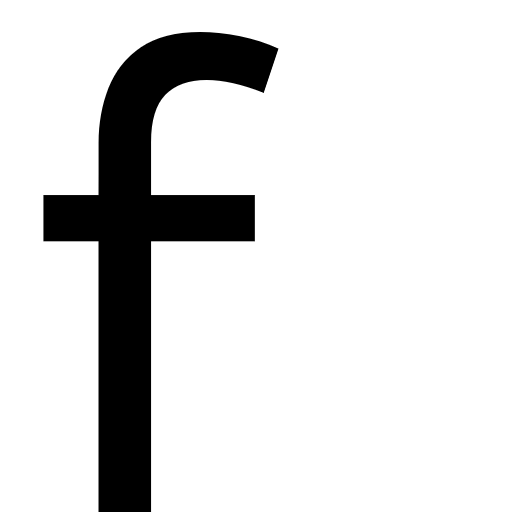ブルック・ハリントン(著), 庭田よう子(訳), ウェルス・マネジャー 富裕層の金庫番 世界トップ1%の資産防衛
著者自らがthe Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) の資格を取得し、ウェルス・マネジャーのインサイダーとして同業者たちへのインタビューを行っている。こうした同業のよしみを活かしてかなり踏み込んだ情報を引き出しているのはさすがとしか言いようがない。
本書で扱う富裕層は日本でよく取り上げられる野村総合研究所の定義よりは一段上で、3,000万ドル以上の運用可能残高が最低ラインとされている。彼らは従来の有閑階級とは異なる種類のエリートであり、みなグローバルで政治的、社会的に均質的な自律的集団とされる。現代ではこうした人々がウェルス・マネジャーという専門家の協力を得て世界的資本を支配している。なお、主に欧米の富裕層が彼らの顧客であり、本書全体を通じて日本の存在感がないのは寂しい。
本書の原題は “Capital without Borders” だが、後半はこのオフショア金融を利用した課税逃れや規制逃れに多くのページを割いている。部外者の多くは見え透いた詐欺とみなすこうしたオフショア金融の利用を、ウェルス・マネジャーの多くは合法で必要なものとみなしている。STEPの研修用マニュアルでもオフショア金融の利用を正当化しており、そこに罪悪感はない。
ウェルス・マネジメントの具体的な戦略についても言及されている。信託を中心に据えながら、財団や法人企業も組み合わせることで、プライバシーを守りながら課税や規制を逃れ、債権者や法制度からの保護を得ることを可能にしている。こうした鉄壁の防御が富の研究を困難にしており、不公平について知る機会が失われている。
佐藤雅彦, 大島遼, 廣瀬隼也, 解きたくなる数学/新・解きたくなる数学
2冊まとめて購入。普通の数学パズル本とは異なり、”解きたくなる” ようなビジュアルが添えられているのがミソ。子供の食いつきも良い。
カシュカイシュ出張
前回訪れてから実に6年ぶり。もう来ることはないかと思っていたが、仕事の都合で舞い戻ってきた。
- やはり日本からは遠い。直行便がないのが苦しい
- 今回はシャルル・ド・ゴール経由としたが、日本初の便が遅延し乗り継ぎに失敗した。幸い、行程のすべての便をAir Franceとしていたため、シャルル・ド・ゴールからリスボンへの便は自動で振り替えられた
- 遅延の関係で、ドアツードアで30時間を要した
- 今回の滞在は不運にして災害事態宣言レベルの低気圧クリスティンやレオナルドに重なり、ほぼ荒天となった
- それでもカシュカイシュ周辺は時折晴れ間が出ることもあるなどまだマシな方ではあった
- 帰りのカシュカイシュ線はダイヤが乱れていたが、多少の遅延のみで済んだ
- ほぼキャッシュレスで生活できるが、多少の小銭はあった方が便利。どうせユーロなので余っても問題ない
- 今は電車の切符もクレジットカードのタッチ決済で購入できるのでありがたい。今回は帰国後の経費精算用にレシートが欲しかったので券売機でICカード (Navegante) にチャージしたが、改札でタッチ決済もできるらしい
- 実際に現金を使用したのは歴史のありそうな土産物屋とコインロッカー程度
- ATMはDCC強制のEuronetが多いので注意
ランドール・マンロー(著), 吉田三知世(訳), ハウ・トゥー バカバカしくて役に立たない暮らしの科学
ランドール・マンローの名前を聞いたことはなくとも、xkcdの中の人と言えばわかる人も多いだろう。おなじみの棒人間のイラストと共にバカバカしい科学を提供してくれる。
内容はいちいちバカバカしいのだが、科学的な記述は大真面目なので子どもに読ませても良い。特にさまざまな投擲の統一モデルは、モデルを作成する際の抽象化を学ぶのに良い教材であり、物理の教科書に載せても良いレベル。